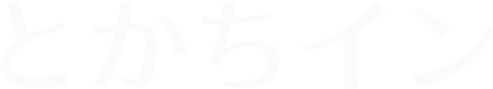謹 賀 新 年
静かな正月の朝を迎えました。昨日は10cmほどの降雪があり冬らしい景色となる。昨年暮れは郵便局のシステム障害により、本州の元従業員(豪州に移住)の住所に郵便物が転送され、会議の出席や請求書の支払いができなかったことをお詫びいたします。こんなことが起こるとは想像しませんでした。
昨年の農場の決算は、収入は2年連続の豊作にもかかわらず、前年と変わらずでしたが、支出はどの項目も1割程度増え厳しい結果となった。農業機械の更新は控え、できる限り自前で修理して使用する。トラクター等の新規購入などは高額で不可能に近く、元が取れません。農業機械、農薬等の資材価格はまた値上げすると聞く。
従業員のベースアップも5%は必ず遂行するので、例年以上に収入増加を見込んだ営農計画を策定しなければならない。昨年仕事が枯渇した10月に加工用キャベツ、加工用馬鈴薯、大豆などを増反して収入を確保する。また16年ぶりに農地の賃貸借が農業委員会から認められ1割程度栽培面積が増える。
JALを再生した京セラの稲盛方式を取り入れて、社員一人一人が経営者となってトップダウンではなくボトムアップも取り入れるようにしたい。社員それぞれに担当部門を与えアメーバ方式に独立して経営するのを目指す。新規就農も加味して法人及び一部独立構成員としての活動もありかなと感じている。既存の高価な農業機械、農地などを安価にシェアー利用をして、初期投資のかかる新規就農を避ける方法も魅力がある。新しい新規就農を取り入れていかなければならない。
そんなことを初夢に、正月あけに帰ってくる従業員と相談してみようと思う。全員が社長待遇で協力しながら営農できることが理想なのか。労働力不足を解消しながら対策を練る。これが一番であろう思う・・・。